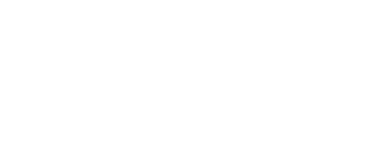『信心』が育むもの 祖母のお話
2018年11月2日
当山では、次月に大きな行事がない場合、封書ではなくお葉書を郵送しているのですが、そのご案内の中で、次のような内容のものを書かせて頂きました。
●『信心』という言葉の対になる言葉はなんだろう。『疑心』だろうか。お題目を信ずる心。お題目を疑いう心。お題目を信ずる者にも疑う者にも災難が降りかかることはあります。今年見舞われた天災はまさにですね。しかし、信ずる者は災難の中に『お陰』を見出すことができる。お題目の加護を感じることができる。『信』が深まると同時に深まるもの。それはきっと『感謝』なのだろうと思う。ふと、亡き祖父母の顔が思い浮かぶ。
結びが非常に含みがちな言葉で終わってしまったので、そのお話を記事にしようと思います。
すでに私の祖父母は、父方母方共に霊山浄土へと旅立ちました。
今日は父方の祖母のお話になります。
父方の祖母は、お檀家様の中でもご存知の方も多く、この本昌寺で生まれ育ったお寺っ子であります。
晩年も健康で元気な祖母でありましたが、父方の祖父が遷化(お坊さんが亡くなることで、「せんげ」と読みます)した頃から、介護施設のお世話になるようになりました。
主に私の母や父の姉である叔母が、定期的にその施設を訪れる日が続き、私も家内や子供と一緒に月に一度顔を見に行くような・・・そんなある日
その時は、母に施設への届け物を頼まれて、私一人で祖母の元を訪れたことがありました。
足が不自由な祖母ではありましたが、頭はしっかりしており、耳も不自由ではなかったので、会話を楽しむこともできます。
その当時、祖母は
「東京オリンピックまで頑張って生きるで。」
ということをよく言っていました。
祖母にとって、東京オリンピックまで生きるということは、100歳を迎えるということなのです。
90歳を超えていることを考えると、その年齢の割には元気な方であったので、100歳を迎えることも不可能なことではないように思っていましたが、その時の私にはその意欲がどこから湧いてくるものなのかがわかりませんでした。
頭はしっかりしているし、耳もちゃんと聞こえている。
しかしながら、足が不自由ゆえに少しの距離でも歩行器を使いながら非常に時間がかかります。
トイレに行くのも一苦労です。
一日のほとんどをベッドの上で過ごし、テレビや本などの多少の娯楽はあっても、60歳離れた孫の私からすると、とても不自由に見えてしまいます。
そんな中で、オリンピックまで生きる!、100歳まで頑張るぞ!という意欲はどこから湧いてくるのか。
何気に感じた疑問。
誰かと一緒にお見舞いに行っていたらなかなか聞けないことでしたが、その時は一人で伺っていたので、それとなく祖母にその疑問をぶつけて見ました。
「おばあちゃんは、なんでそんなに頑張って生きようって思えるん?」
その時、祖母が返した言葉はたった一言でした。
「毎日のご飯がおいしいからやで」
なんとも言えない気持ちになりました。
あぁ、祖母はないものに目を向けず、あるものに目を向けているんだなと。
同時に、自分はついついないものばかりに目を向けて悲観ばかりしているなと。
その心の根底にあるもの、私と祖母の大きく違うところ。
それは『感謝の深さ』だと感じたのです。
祖母の『感謝』はどこで育まれてきたのか。
90年を超える様々な人生経験の中で育まれてきたとは思うのですが、その中に『お題目への信心』があると思うのです。
お題目が私を守ってくれる。お題目が家族を守ってくれる、お題目がお寺を守ってくれる。
小さい頃から祖母と同居してきた私は、『お題目への信心』という点で、祖母から大きな思いを感じるところが多々ありました。
何が起きようと『お題目への信心』が自分自身に『安心』と『加護』を頂けていることに疑念を持たない。
それゆえに『感謝』が生まれてくる。
論理的に考えると、こんな感じだと思うのです。
私は到底祖母の足元にも及びません。
それどころか、大変な強欲人間です。
ですが、祖母のように安らかな心で生きていけるなら、それは単純に幸せなことだろうなと思いますし、そうなりたいと願ってもいます。
よく「感謝せなあかんなぁ」と言いますが、『感謝』はせなあかんものではなく、自然に湧き出てくるものが理想だと思います。
どのようなアプローチで自分自身の『感謝の心』が育まれるのか。
それは人によって種々様々ではありますし、その答えも一つではないと思いますが、私の祖母は『信心』によって育まれたものに感じるのです。