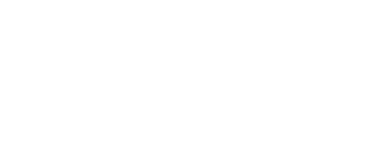節分 立春に思いを馳せて
2020年2月5日
節分の法要の後、少しだけお話をさせて頂きました。
(文字化)
本年の当山の節分会に、よぉお参り下さいました。
少しだけお時間を頂戴して、お話をさせて頂きたいと思います。
本日は節分なわけでございますけれども、皆さん、節分というと何をイメージされますでしょうか?
私はやはり豆まきなんですね。
小さい頃は、数え年の分だけお豆を食べたことが思い出されます。
豆まきに使われる『大豆』は、魔除けの意味合いがあるそうで、旧暦の大晦日である節分に豆をまき、そして豆を食して、来たる年の安寧を願ったそうでございます。
豆まきの歴史を調べてみると、文献上の最古は1425年だそうです。
これは意外でした。
私は、様々な文化が隆盛されたであろう江戸時代だと、勝手に思い込んでおりました。
思い込みはいけませんね。
そんな歴史ある豆まき行事ですが、ご家庭で豆まきをされている方も少なくなってきたのではないでしょうか?
お家で豆まきしてるよ〜という方、手を挙げて頂いてもいいですか?
あっ、そんなに少なくはないみたいですね!
今日は小さな子供さんもお参り下さっていますが、この子たちが大きくなって
「節分というと、何を思い出しますか?」
と尋ねた時、
もしかしたら、
「巻き寿司!!」
と返ってくるかもしないなと思っていましたが、そんなことはなさそうですね。
とはいえ、ご家庭単位で豆まきをする風習は、昔に比べると少なくなったとは思いますし、豆まきのストーリーが、何を意味しているか、知らない方も多くなってきたのではないかと思います。
そもそも鬼というものについて、どのように捉えたらいいのでしょう?
鬼に豆を投げて、鬼を追っ払う、鬼をやっつけるという豆まきのストーリからは、何か外敵に対して、それらが寄ってこないようにしているようなイメージを描いておられるかもしれませんが、私は、『鬼は内なるもの』と考えております。
誰からも慕われるような方であっても、過ちを犯してしまうことはありますし、悪いとわかっていながらも悪事に手を染めてしまうこともあります。
逆に、今まで悪事を重ねてきたような者でも、自分の過ちに気付き気付かされ、善行に励む方もいます。
そんなことを考えると、『鬼』というのを別の言葉で置き換えたならば、『弱き心』になるのかなと思うのです。
立春を迎え、そんな自分の弱き心を追っぱらおう!
節分は、そんな行事なのかなと受け止めています。
じゃあ、『強き心』とはどんなものなのか?
それは、自分の弱さを知っていて、それを認めることのできる心だと思うのです。
令和2年が、皆様にとって実り多き年であることをご祈念致します。
本日は、ご参拝ご苦労様でございました